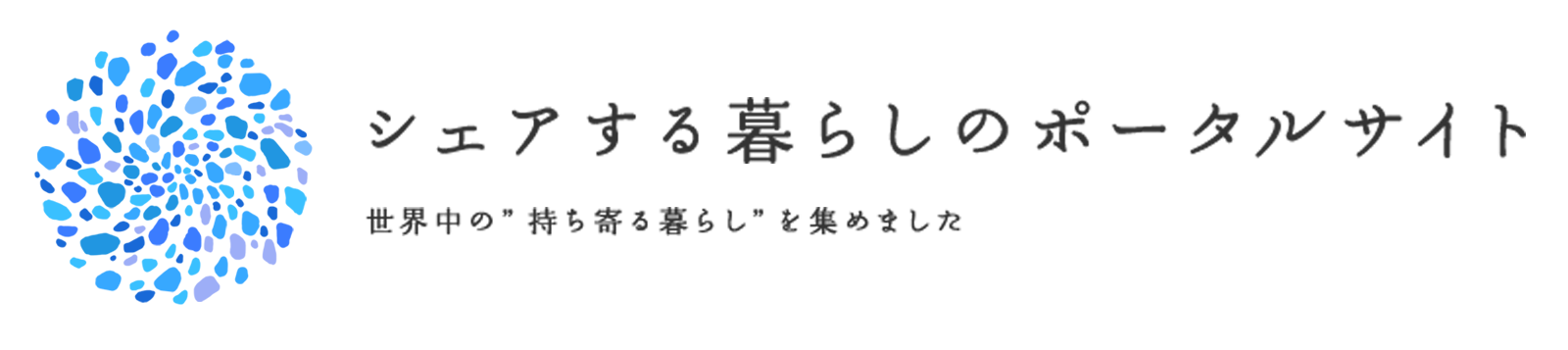「子どものまち」の取り組みがこの数年、日本各地で続々と始まっている。
多くの取り組みがルーツとするのが、ドイツのミュンヘン市で20年前に始まった『ミニ・ミュンヘン』。
2年に一度出現する「子どものまち」では、子どもたちは働き、遊び、また選挙などを通して社会を学ぶ。キーワードは、「自立心」と「ファンタジー」。
大人たちの固い頭による制約なしに、子どもたちはお互いに関わり合い、時には衝突もしながら「まち」を作り上げていく。
日本でも各地でさまざまなコンセプトのもとに、さまざまな形態で行われているが、なかでも、ミニ・ミュンヘンに一番近いと評判なのが、高知県高知市の『とさっ子タウン』。
8月最終週の土日に開催された、その『とさっ子タウン2011』に見学に伺った。
市民になって働く
とさっ子タウンは、今回で3回目の開催になる。場所は、りょうまスタジアム、高知市の自転車競技場だ。
とさっ子タウンに参加できるのは、小学校4年生から中学3年生の子どもたち。2日間続けて参加できることが条件となっている。
事前に登録が必要で、今回約300人が参加した。
とさっ子タウンの仕組みは、下記のようになっている。
① 市民登録局で受付をする
② まちの約束ごとを30分学び、支度金をGET!
③ ハローワークでやりたい仕事を選ぶ
④ 選んだ仕事場へ行き一定時間仕事をする
⑤ 仕事が終われば銀行に行き給料をもらう
⑥ 税務署で税金を支払う
⑦ お金は、まちの中で使えるし、銀行に貯金することもできる
⑧ 就労経験を積み資金を貯めれば店の経営者になったり、新規店舗をはじめることができる
⑨ まちの課題点等が生まれてくれば、議会をつくったり、市民選挙を実施して、解決策を講じるなど、子どもたち自らがまちの運営を行う
—–(以上、とさっ子タウンの資料より引用)—
仕事は、新聞社や警察、写真屋さんなどさまざまで36業種(今回)に及ぶ。
働くだけでなく、商店街やゲーム広場など遊ぶ場所ももちろんある。
そして、市長選挙も。
まさに「まち」なのである。

市民証の写真を撮ってくれる写真店
子どもを信じて見守る大人たち
当日、まずは実行委員会副委員長の真辺さん(大学生)が概要を説明。
実行委員会は90人ほどの規模で、社会人と学生がほぼ半々、委員長と副委員長は大学生が務めている。
子どものまちにはさまざまな形態があるが、とさっ子タウンの場合、事前の準備に子どもたちは参加しない。まちの骨組みは実行委員会でしっかりと組み立てられるし、当日は後述する専門家スタッフが参加するなど、大枠の作り込みは大人(学生含む)の手でしっかりと行われる。
ただし、そこは子どものまち。
当日、まちの中で起こることは、子どもたちのこと。
その点に関しては、明確な共通認識があり、「子どもたちのチカラを信じよう!」と、先回りしてあれこれ言わず、困っていたらはじめて声をかけるくらいのつもりでいよう、というスタンスが明文化されている。
概要説明を通して伝わってくるのは、ここでの大人の役割は口を出すことではなく、子どもたちがさまざまな体験をするための環境や状況を作っていくということ。そうした中で子どもたちは、主体性をもって、幅のある体験を楽しむことができるのだ。
「税金納めてくださーい」
観光ツアー(見学)で、まちの中を案内してもらった。
小学生のガイドさんを先頭に、大人3人がツアー客の証である段ボールのベストをかぶって、ツアーに出発。
子どもたちの顔を見ると実にキラキラとしていて、楽しんでいるのがすぐに分かる。
あちこちで、仕事に遊びに夢中な様子が見られた。
目に留まったのは、議員選挙の選挙活動。候補者がポスター掲示をして回っている。
「とさっ子放送局」の番組プログラムの一環として、館内放送を利用した選挙演説もあるということだ。
今回は、前回から半年しか経っていないので、市長選ではなく議員選挙なのだそうだが、例えば、実際に市長によって税率の引き下げがなされたりもしているそう。この選挙、単なるステイタスにとどまらない実のある選挙のようだ(※1日目の選挙時の公約を、2日目には施策として実施するという仕組みになっているとのこと)。

議員選挙立候補者のポスター
さらに、見学していると、「税金を納めてくださーい」「忘れていませんか―」とマスコットを持って訴えながら歩いてくる子どもたちに遭遇した。
とさっ子タウンでは、前述のとおり、働いたら銀行でお給料を受け取り、自分で税務署に行って納税する仕組みになっているが、漏れというかなんというか税金が納められないケースがあるのだそうだ。
税務署には、[税金の使われ方]という手書きの模造紙ポスターが貼り出されていた。
それに加えて、税務署で働く子どもたちが、納税の呼びかけをして歩いているということのようである。税金も、まちの仕組みの重要な部分。

税務署には「税金の使われ方」のポスター
保護者の目を気にせずに振る舞える場
実は、大人は簡単に中を覗けるわけではなく、観光ツアーは実際に中を見ることができる貴重な機会である。
見学できる大人も、とさっ子タウンの関係者以外には、教育関係や子どものまち関係者など限られていて、しかも、滞在を許される場所は、“まち”のはずれに壁を隔てて併設された「大人カフェ」、決められたツアー以外では子どものまちに入ることはできない。
子どもの保護者たちは、観光ツアーでも子どものまちに入ることはできず、会場の一階(子どものまちは二階)にある待合室で過ごすことになっている。こうした仕組みによって、子どもたちは保護者の視線を気にせずに、思い切りやってみることができるのだろう。
待合室では、とさっ子タウンの数時間前の様子を映したVTRが大きなビジョンで流されていた。
“子どものまち”といっても、保護者がついつい口を出してしまうのは、どこでもありがちなことなのだと、以前別の場所で聞いた。
ある都市では、理解を促すために積極的にボランティアとして入ってもらう工夫をしているそうだが、とさっ子タウンの場合には、上記のように場所を切り離す方法をとっている。
子どもの立場で考えれば、直接口を出されなくても、見られていれば気になるもの。この方法は、自分が子どもだったらと考えるととても良い方式だと感じた。
とはいえ、やはり保護者の知りたい気持ちに応えることや、また活動への理解や子どもたちとの関わりを促すことは重要。このため、タウン内で「とさっ子新聞社」が発行している『とさっ子タイムス』を持って帰ってもらったり、タウン内で働いた内容が記録される『市民証』をネタにして、家で親子の会話を楽しんでもらう工夫をしているそうだ。後日、そうした会話の様子がFAXやメールで事務局に送られてきているとのこと。

市民証。冊子のようになっており、ID部分のほかに働いた記録やお店開設の記録、預金など、とさっ子タウン市民としての活動が記録するページがついている。
子どもたちに本物の体験を
とさっ子タウンの大きな特徴と思われるのが、先ほど触れた専門家の協力である。
観光ツアーで回った時にも、街角の交番に本物のお巡りさんがいて驚かされたし、健康診断のブースには医師や看護師さんの姿もあった。
全36職種のほとんどに、その道のプロが協力しているのだそうだ。
そうした専門家の方たちの参加のもと、本物の道具を使ったり、プロのお仕事を教えてもらったりしながら、子どもたちは仕事を楽しむ。

ナースセンターには看護師さんの姿が
その道の専門家の協力、中には「高知らしい」というものもあるそうで、そのひとつは、なんとバー。本職のバーテンダーさんと一緒に、子どもたちもオリジナルカクテルを開発したりしているとのこと(もちろんノンアルコール)。
もうひとつは、箸拳というもの。
箸拳というのは、箸を使って数を当て合う高知伝統の遊びということで、こちらのコーナーには、なんと、和服のお姉さま方の姿があった。本物の芸妓さんなのだそうだ。
普通ではちょっと考えにくいかもしれない、こうした「高知らしさ」がすんなりとなじんでいるのが、かえって不思議でとても印象的である。

和服姿が目を引く箸拳道場
副委員長さんに長い時間、丁寧に対応していただいた後、実行委員会の中心メンバーでいらっしゃる畠中洋行さん(NPO高知市民会議/高知市市民活動サポートセンターセンター長)にお話を伺うことができた。
まずお聞きしたかったのは、実行委員会とは別にこれだけの規模で大人たちの協力を得るのは大変なものではないのか、ということ。
「やりたいことが明確で、しかもそれが、子どもたちのこと。子どもたちが高知を好きになることなので、協力が得られる」と畠中さんはいう。
同時に、専門家や企業なども、自分たちの仕事(やっていること)を子どもたちに知ってほしいという思いが背景にあるとも分析してくださった。また、実際に一度見学してもらうと協力をしてくれるようになるのだそうだ。
なるほど、確かにあの子どもたちの姿。説得力は抜群なのかもしれない。
もちろん子どもたちが主役ではあるけれど、しっかりした企画の背骨があり、それに沿った運営スタッフの様々な工夫と努力がある。とさっこタウンの場合には、もう一つ、外側の大人たちの関わりがあるというわけだ。
当日の専門家としての関わり、協賛など、有形無形の支援や協力がとさっ子タウンに奥行きや厚みを加えているのであろう。
子どもたちと運営スタッフという単純な図式ではなく、もっと大きなものに包まれた塊として、『とさっ子タウン』はそこにあるのだと私には感じられた。
子どもたちが専門家と過ごすことで仕事を知り、子どものまちを通して大人の街に興味を持って、自分たちの街・高知を好きになる。それを面白がる大人たちが集まって、とさっ子タウンを盛り上げている。
大人にとっても子どもにとっても、夢見て、実現する「ファンタジー」が、そこにはあるのではないだろうか。【了】
文責:矢田浩明