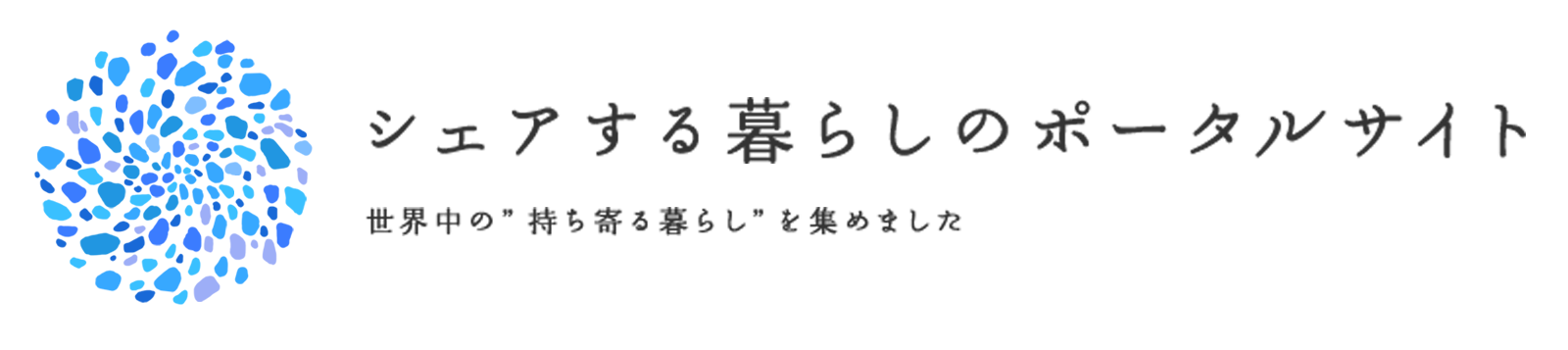京都・大山崎の風土と自然に惹かれ東京から移住した夫妻が、「毎日の暮らしに寄り添うコーヒー豆を」をコンセプトにした小さなコーヒー焙煎所をはじめた。お店は駅から歩いて15分のだらだら坂を上がりきったところにあるレトロビルの一室。営業は木曜日と土曜日の10:00~15:00だけ。インターネットショップとイベント出店だけでコーヒー豆を販売していたのが「大山崎COFFEE ROASTERS」の始まりで、焙煎所を兼ねた店舗を開店しても、もとのスタイルを損なわないためだ。

店頭では焙煎後3日以内の豆のみを販売、鮮度を守るため挽き売りはせず全て豆のまま
これまでの東京での生活から仕事も住むところも180度転換し、移住先でごく自然に地元にソフトランディングしていった中村夫妻。どんな経緯があったのかお話を聞いた。

初めてきたその日に「ここ」と決めた
中村佳太さんは関東の育ちで、理系の大学を卒業後、東京のコンサルティング会社に勤めていた。中村まゆみさんは京都の宇治で育ち、大学を卒業後、ロンドン留学を経て東京でOLとして働いていた。そんなお二人が出会い2010年末にご結婚。結婚して「家」を意識するようになってから、仕事でほとんど家にいないことによくないと思い始めていたという。
「ちょうどそんなときに、2011年3月の震災があって。「もっと一緒にいるべきだ」と思っていても、相変わらずずっと忙しいまま。これは自分たちの望むライフスタイルではないなって」
自分たちのしたい暮らしをするにはどうしたらいいか?2人でできる仕事をしよう、静かな環境でみどりがあるところにいこう。そう話し合ったという。その後、具体的な移住先を探し始めた。興味がある街を目指して、九州や関西方面に行ってみたりを1年かけて。そんななかでの大山崎との出会いをこう振り返る。
「駅おりたときの雰囲気がよかった。カフェ、ホテル、神社があって…。大山崎は大阪から京都のあいだで、ぽこっと田舎が出現する。その雰囲気が気に入った。初めてきたその日に「ここ」と決めたんです」

店の窓からのぞむ風景
「コーヒー」を仕事に
移住先を探しながら、“2人でできる仕事”については並行して考えていた。二人ともが好きなことがいい。「なにしたら楽しいかな」「食っていけるかは別にして、とりあえずあげてみよう」と、ふたりで紙に書きだした。本・図書館など書き出したアイデアのうちのひとつが、当時ハマりはじめていたコーヒー。趣味が高じて焙煎のワークショップに参加し、豆を焼くことそのものに興味がでてきていた。

「コーヒーならと、もちろんカフェも検討しました。ただ、カフェをするには場所が必要。もし場所があったとしてもどれくらい人がくるかわからない、街のこともまだわからない。実際、店舗兼住居を探していたけどなかなか物件はなくて」
それで、大山崎へ移った翌年の2013年6月、まずはネットショップ限定で「豆の販売」からはじめることにした。店舗経営でいうとちょっと変わった流れかもしれないが、(ネットショップのBASE、クラウド会計ソフトのfreee、カード決済システムsquareなど)最新のテクノロジー好きで「つかえるな」と思ったらいち早く取り入れようとする佳太さんのスタンスに、逆に新しさがあった。
はじめは東京の友人が買ってくれる程度からスタートしたが、それだけではもちろん成り立たない。そんな折、開設当初から大山崎の商工会の方々に相談をしていたところ、駅前の観光案内所を使ったらという提案をもらった。そして開業二か月後から、月2~3回ポップアップショップとして駅ナカに立つことになった。ネットショップに加えてイベント出店というやりかたもあるんだなと知ったのもこれがきっかけだし、この活動が地元新聞にとりあげられたことで、移住後早い段階で街の人と知り合うきっかけにもなったという。

イベント出店にて
「とりあえずやれることからというミニマム思考
あくまで実店舗は後からはじめたこと。とりあえず“ミニマム”に店をあけよう、必要なら後からちょっとずつ増やしていこう。こうした経緯で、店舗でのドリンク販売はせず試飲のみ、週2回計10時間だけあいている今までにない形のお店が生まれた。
「ドリンクを販売したくなったらあとで喫茶許可をとろうと“とりあえず”ではじめたことだけど、結果的にこのスタイルが性に合っていた」
と佳太さんは振り返る。試飲して、おしゃべりして、豆を買ってかえる。これが自分たちの店のスタイルになった。

お店には大きなテーブルがひとつ
お客さんと自分たちの距離を縮めたいから、カウンターで対面するのではなく、1つのテーブルでドリップとお客さんの座る場所を一緒にしようということは、はじめから決めていた。お客さんとお客さん同士の距離は当初は想定していなかったが、この空間なので、自然とお互いに会話がうまれる。
「そんな風にここでつながった人同士が、その後イベントを一緒にやることになったなどのエピソードを聞くと嬉しい」
週2日しかあいていないことで、逆に出会いが凝縮されている気がするのは私だけだろうか?
街の「情報交差点」に
最近では、お客さんから移住、お店やゲストハウス・アトリエをもちたいという相談を受けるようになってきた。人をつないだり、知っている空物件を紹介したり、役場の人を紹介したり。また、自治体の枠を超え、地域の「良いモノ・良いトコロ」を残したいという想いをもって集まった住民有志の「oYamazaki まちのこし Project」に参加して街を舞台にした自主映画を作ったりもしている。
今では、お客さんの7割以上が地域の方になっていることに、自分たちがびっくりしていると笑う。

ハンドドリップワークショップでの一コマ
本当にいいものはそのやり方では創れない
経歴だけ聞くと、戦略的にコンセプチュアルに考える人かと実はインタビュー前は思っていたんです、と伝えるとこんな言葉が返ってきた。
「理系・コンサル出身としては、この仕事をはじめて勉強になるんですよ。予算計画にせよ戦略にせよ、人間が事前に考えうることに限界があるということに気付いた。だって、今お店で起こっていることを、僕が事前に予想できたかというと何ひとつできなかったと思うんですよ。だから、与えられた制約のなかでできることをとりあえずやってみることの方がおもしろいということに気づきました。
でも、ひとつだけ最初から意識していたことは、コンセプトから入らないようにしようとは気をつけていた。前職ではそれこそ、コンセプトが大事で、そこからブレイクダウンをして仕組みをつくっていくというのが基本的な思考パターンでしたが、それじゃないことをやってみたかった。僕の感覚では、そのやり方だと「中の上」はつくれるけど、本当にいいものはそのやり方では創れないんじゃないかなというのがあって。自分自身もコンセプチュアルなものよりも、自然発生的にやったらこうなったというものに惹かれるというのもある」

京都の金属職人と制作したオリジナルのドリップスタンド
望んでいたライフスタイル。一度手に入れたら拡大は考えていない。人も雇うつもりはない、2人でできる仕事をやっていく、そこはぶれない。
*
風にのってたまたまこの地に降り立った種が、その地に根付き芽吹いた。植栽された鮮やかな花ではなく、まるでもとからそこに咲いていた野花であるかのような。こんなに風景に一体化して馴染んでいるのは、きっとお二人の人柄なのだろう。
【了】
文責:山下ゆかり
【編集後記】
毎日のむもので実は鮮度が命のコーヒー豆。そこに(まるで一昔前の魚屋のように)頻繁に人々が立ち寄る街の交差点になる可能性がある。コーヒーやお店をもつことにこだわりすぎなかった夫妻だから、境界を軽々と超えていろんな活動をとおして街とつながっていった。「場」の重要性と「場」にとらわれすぎない絶妙なバランス感覚が、新世代を感じさせる。ぜひあなたも一度店を訪れてみてほしい。