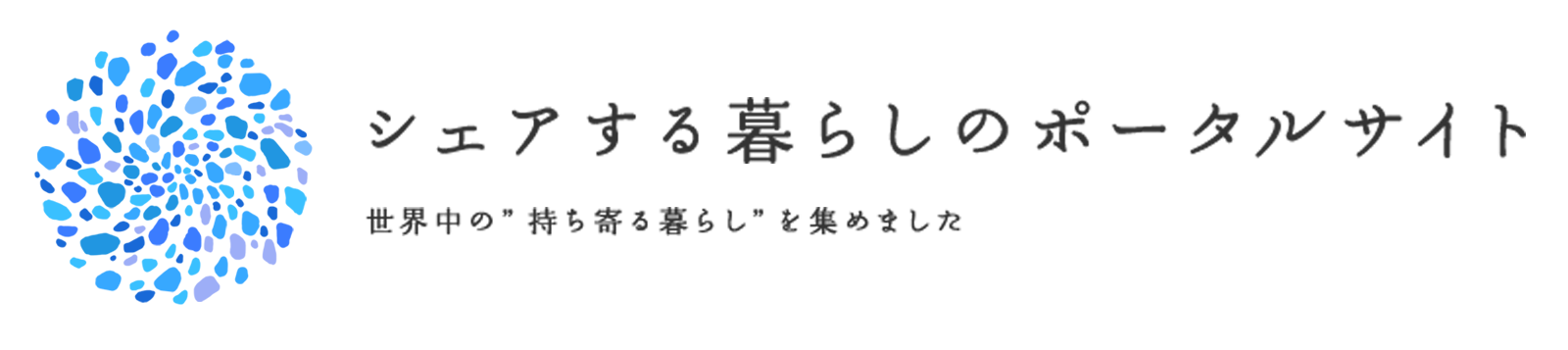仕事も家庭も、いつかの夢もいまの生活も―。「どちらかだけ選ばないといけない人生なんてナンセンスでしょ?」という価値観は、昨今もはや特異なことではない。では、“二兎を追う”暮らしを実現する時に、大事なことはなんだろうか。どっちも求める欲ばり者はイタイ目にあうという社会通念とは逆で、「本当に実践している人」の側に寄ってみても利己主義的なにおいはしてこない。むしろ、仕事も家庭も、夢も生活も、一方を他方の言い訳にせず、両方に当事者意識をもって向き合っているような気がするんだけど…。もっと近寄って確かめてみたい。
今回お話しを聞くのは、自宅の一部にておもちゃ屋をひらいて8年になる横尾泉さん。「住み開き」の先駆者だ。

二人の小学生のお嬢さんの母でもある
やれる範囲でしかやらない
保育士だった横尾さんは結婚を機に退職し、東京の郊外の新興住宅地にマイホームを購入し移り住んできた。そして当時、専業主婦として一人目のお子さんの子育てのなかで行き詰っていた。元保育士としての理想と現実の自分とのギャップに苦しんでいたという。とにかくそこから抜け出したい一心で、以前からすこし興味があったおもちゃコンサルタントの資格をとりにいくのだが、これが運命のきっかけとなる。
「これまではおもちゃって子どもの遊び道具くらいにしか思ってなかったんです。でもおもちゃのことを勉強するなかで、いいおもちゃは子どもの力を引き出してくれることを知って。その子の“今”を表現する手助けをしてくれるんです」
おもちゃの素晴らしさに出会い、これを伝えていく仕事がしたいという新たな想いが芽生えた。しかし当時、2人目の妊娠中でもあり─
「生活と仕事を別々にしたくはなかった。何よりもリスクを取りたくなかったな。例えば家賃を払って店舗を借りるとなると、一日中お店にたたなくていけなくなるので、子どもも保育園に預けなくてはいけなくなるし、人も雇わなくてはいけなくなるし…っていう。一人でやれる範囲でしかやらないと決めてましたね」
こうして2005年、自宅の六畳一間を予約制のおもちゃ屋として開業する。店舗用に大掛かりな改装などもせず、自宅用の玄関から「おじゃまします」と入るスタイル。初期投資を抑えるという理由ではあったが、“場所見知り”せず、自分の家で過ごしているのと近い状態で子どもがおもちゃを選べるというのがウリのひとつになった。また、お母さんたちにとっても、普段友人や夫に話せないようなことでも話せる場にしたいと考えていた横尾さん。接客では、おもちゃの話をきっかけにたくさん会話をする。やってみるなかで、物理的に(家を)開くだけではなく、自分からまず(心を)ひらくと相手もひらいてくれるはず、という想いは実感にかわった。

文字通り「アットホーム」な店内でリラックスする子ども
しかし、難しさもあった。自宅の一部だというと卸メーカーに信用してもらえず、取引に応じてもらえない。これは!と思うおもちゃをセレクトしても店に並べられない。当初の決断とは裏腹に、いつかはちゃんとした店を持たなくては…と思い詰めていた時期もあったという。
「子どもに背中を見せる」を続けていく原動力に
生活と仕事を別々にしないというと耳触りはよいかもしれないが、現実はキツイ。もともとおもちゃは足の早い商品でもなく、苦心して仕入れても過剰在庫を前に途方に暮れる日々。店用の六畳一間の押し入れは満杯、置く場所がないからいつでも子ども部屋の一角はダンボールが山積みで、何度子どもに泣きつかれたか。当然、営業はずっと赤字続き(利益がでるようになったのは最近のこと)。こんなにやっているのにどうして…と何度もくじけそうになった。何度も、もう辞めようと思った。でも─
「自分の子どもたちに、夢をもつとはどういうことか、働くってどういうことかを身をもって示しているつもり。それがここまで続けられた一番の原動力かもしれない」

生活と仕事を別々にしないということは、なにも物理的な時間や空間のことだけではなく、感情や想いもない混ぜになるということ。だから横尾さんの「自分の子どもが店を続けていく原動力」という言葉にはリアリティがある。
仲間とつながり地域へ活動をひろげる
子どもたちが小学校にあがり時間がとれるようになってからは、自宅ショップを飛び出して、出張おもちゃ屋、ママ向けのおもちゃの講座やワークショップなども積極的に行うようになった。外へ出ることで縁も少しづつ広がり、さまざまな企画に声を掛けてもらうことも増えた。2年前からは、想いを同じくする仲間とモノ・コト企画というユニットを立ち上げ、「たまおもちゃ市」や「モノコト市」などのイベントを主催している。子どもたちを中心に多世代の人を巻き込みながら、作り手と使い手が交流できる場として会を重ね、今や多摩地域の定番イベントになった。



気がつくと、8年が経った。たった独りではじめたことだったのに、今ではこんなに仲間やつながりが増えている。開所当初からいつかはやりたいと思っていた地域に向けた活動が、今や自分の仕事の中心になっている。かつて、自分自身も囚われていた「店たるもの店舗を構えるべし」という世間の常識にのまれないで、自分のこだわりを譲ることなく、さらに多少の赤字なら目をつぶって堪えてここまで続けてこれたのは、「住み開き」というリスクを最小限に抑える方法をとっていたからともいえる。想い×仕組みがうまくかけあわさって実現した。
そして「おもちゃ屋」を超えていく
今年の2月、世界最大のおもちゃ博が開催されるドイツを訪れた。憧れのドイツの老舗おもちゃメーカーとの取引を得るなど収穫の多い渡欧だったが、特に横尾さんにとって印象深かったのが、ドイツの教育思想家・フレーベル生誕の家を訪れたときに聞いたエピソードだ。


ドイツの教育思想家・フレーベル生誕の家
「幼稚園=「キンダーガーデン」は彼の造語なんだそうです。子どもは生まれながらにして育つ力を持つ種である。子どもの周りの大人はその種を育む役目、土のような存在。だからキンダーガーデン(子どもの庭)という名前になったという…それ聞いたときにジーンときました」
種が発芽するには、適した環境と適切なお世話が必要なのと同様に、子どもの発育にもこれらが大きく作用する。「環境として適したおもちゃとは子どもの力を引き出すもの」とフレーベルは言った。子どもが本来もっている力、想像力・つくり出す力…。ああそうか、やっぱり自分はおもちゃを通して子どもたちの力を開花する手助けをしたいんだと再確認した。そして、これからの自分のテーマは、このことを実践としてどうお母さんたちに伝えていけるのか?だとも。横尾さんは、旅行中も帰国してからも、ずっとそのことを考えている。 その取り組みのひとつとして、国立にあるやぼろじで毎月1回開催している「木のおもちゃの日」がある。元々は古民家の広い和室を開放し、木のおもちゃで遊ぼうという企画だ。
「この内容をさらに濃くしていきたい。一時間ただおもちゃがあるところで遊ぶだけなら公的な児童館とかわらない。それだけじゃなく、お母さんたちに向けても気付きや考えるきっかけとなるワークショップ形式の場にしていきたいなって考えているんです」

自分なりの子育て支援を追及していきたい
おもちゃを通して親子の心と心がつながる時間をつくるお手伝いがしたいという想いはますます加速する。六畳一間から世界へアクセスするチッタは、今や地域の・お母さんの・子どもの庭となった。【了】
(文責:山下ゆかり)
編集後記
こんなことできたらいいなと思うことは誰にも一度や二度はあるだろう。横尾さんにとっても、忙しい子育て生活のなかである時ふと「おもちゃ屋ができたらいいな」と思ったにすぎない。だけど、実際にやっていると人とやっていない人、継続している人途中で挫折した人─その差はいったいどこにあるのだろう? 横尾さんのお話しは、そんな素朴な問いに対するヒントで一杯だった。やれる範囲ではじめられるという観点で、住み開きというアイデアは大いに参考になる。さらに、続けていくなかで起こるさまざまな葛藤や困難については、横尾さんらしい数々のシェアする暮らしの知恵で乗り切ってこられたのがわかった。さて、あなたにとっての原動力は何ですか?