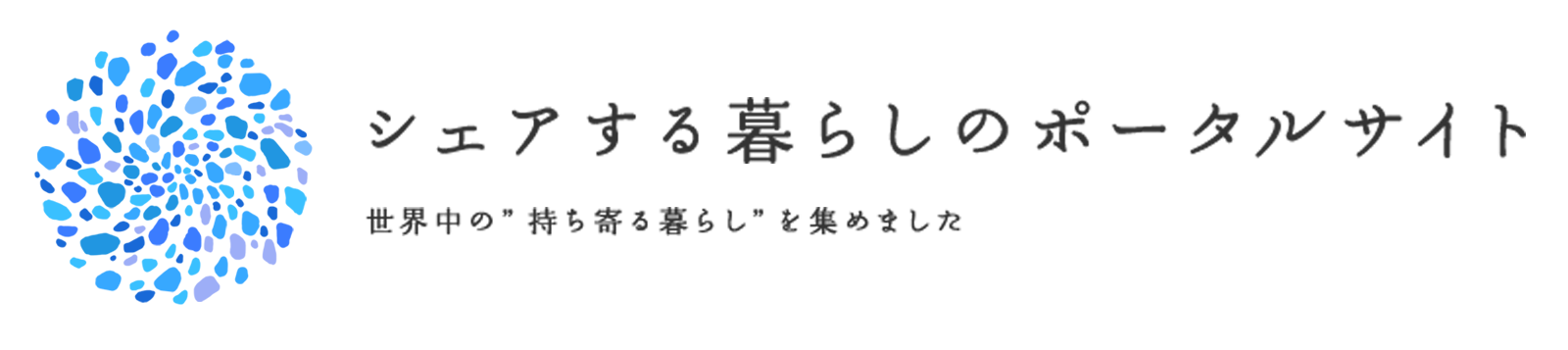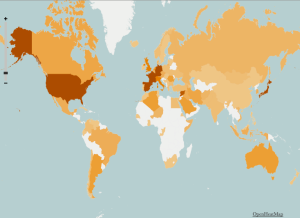ベルリンから電車で1時間ほど離れた人口約50万人の地方都市・ライプツィヒ。旧東ドイツに位置するこの地は、19世紀後半に工場地区として開発され工場労働者のための集合住宅が多く建てられるが、東西ドイツ統一後は空き家に転じ、最も衰退した地区として忘れさられていた。それが今では、ベルリンに次ぐクールな街※1として注目され、若者やアーティストなどを中心に様々な国から移住者が集まってきている。
縮小する都市における再生の成功モデル──その一翼を担ったのが、実は日本人の建築家、アーティスト、研究者らが起こしたあるプロジェクトであったことをご存知だろうか。空き家をセルフリノベーションし、日本というテーマを用いて人々が集う家として再生した「日本の家」だ。
「日本の家」では、ごはんの会、コンサート、美術展、日本文化ワークショップ、子どもと家族向けのイベント、学術的シンポジウムなど多岐多分野に渡る活動を近隣住民と協働して行ってきた。特に週2回開催している共につくって食べるごはん会には毎回100人以上が集まり、人々にとって大事な居場所のひとつになっていることがわかる。
立ち上げは2011年7月。実は当初は3か月限定のプロジェクトのつもりだったというが、6年過ぎた今なお現在進行形だ。今回は、プロジェクト立ち上げ当初からの中心メンバーである大谷悠さんに、活動を改めて振り返って今思うことを聞いた。

「そのときはこんなことになるとは思ってもいなかった」大谷さん
■自分のために「場所」が必要だった
日本の家は、大谷さんにとって何でしょう?作品というかアート?
「それは自分のなかに明確に答えがあって、“ぼくらの家”なんですね。
というのも、当時僕はドレスデンという違う街に住んでいて、もう2人の日本人のアーティストと建築家と共に活動拠点を探していた時に、たまたま「ライプツィヒが空き家を使いたい人に仲介してくれるよ(プロジェクト・ハウスハルテン ※2)」と教えてもらって移ってきたんです。助成金の申請も無事通っていざライプツィヒで活動をはじめようとしたものの、この街に友達がまったくいないし、ほとんどドイツ語もできない状態だった。人と会いたい、自分から何かしたいというモヤモヤを抱えた状態で、自分の生活のために“場所”が必要だと思ったんです」
“ぼくらの家”ですか。もう少し詳しく言うと?
「共になにかする場所というのかな。家族も身内も知り合いもほとんどいないなかで、助け合わないと自分の生活も成り立たない状況で。プライバシーや閉じるという一般的な家の概念と真逆で、仲間や友達が寄ってくる集まる場所というイメージ。
今考えると、自分の生活をおもしろくしたいというのがコアにあって、場所をつくったらそこに僕と同じような状況の人が集まってきて。誰かとつながりたいとか友達を増やしたいとか、ごはんを一緒に食べたいとか、(アーティストなら)発表をしたいとか…。自分の生活をおもしろくすると、他の人の生活もよくなって、それがどんどん街の方にもひらけていくというか、そういうプロセスだった」
大谷さんの考える“場所”って?
「実は場所と空間は僕にとって全然違うもの。空間は物理的に空いているスペース。場所はそこに“人間”がはいってくる。思い入れや、記憶や、関係が生まれることとか、人間の活動をとおして表出するもの。これはイーフー・トゥアンの『空間の経験』に出て来る定義なのですが。
で、空き家は“空間”だから、僕らはそこに“場所”をつくれる。空き家がもし最初から“場所”だと、僕らはなかなかそこに入っていけない。ライプツィヒの空き家活用の場合、時代背景上、大家さんと空き家の関係が切れている、つまり空間だった。都市のなかにまだ空間が残っている(まるで真っ白なキャンバスのように)、ライプツィヒはそんな街だった」
「空間」の状態から、どうやって「場所」になっていくんだろう?
「それはもうlarning by doingで。当初は訳もわからずはじめて、一体この先どうなるんだろう?と。そのうち少しお金がまわるようになって、いろんな人が関わってくれるようになって、自分の「生活」がそこにできていって。場所をつくっていくなかで自分が学べることが大きいから、就職するよりここでやれることのほうが経験として大きいのではないか?と思いながら今に至る感じで。
ライプツィヒにきて特に思うんだけど、貧乏であることと貧しいことは違うのと同じように、金持ちであることと豊かであることは違うなと。今の僕の状況は、貧乏だけど豊かだなって思うんです。一緒にごはん食べる仲間がいて、気遣える人がいて。もちろん、この次のステップでお金のことは抜きにはできないが、最終的にどういうことがしたいかというときに、貧乏でもいいけど貧しくはありたくないなと思うんです」
“ぼくらの家”だったものが“みんなの家”になったのを意識しはじめたのは?
「どちらかというと、立ち上げた当初は“みんな”を意識しすぎていましたね。社会的なことをやらなくてはいけないという意識が強くなっていて。自分がサービスを与える側でなければいけないというプレッシャーが当時はあった。だけど2014年末からごはんの会をはじめてから、まず自分たちが楽しくないとだめだなっていう原点に戻って。自分たちが楽しい場所をつくれると、そこに人が集まってくる。難民・ホームレス・孤独な人…なにかつながりを求めている人が自然と集まる感じがあって。それが結果的に社会の潤滑油になるというか、行き詰っている人に少し希望を与えられるような空間や時間をつくれるんだなとわかった。これは関わってくれている人たちのおかげで実現しているんです。」
今、自分達として評価してみて「日本の家」はこの街にとってどういう存在になっている?
「国別にみるとのべ90か国以上の人が訪れているんです。日本というキーワードは結果的によかった。こっちの人にとって日本は、遠くて、戦争はしそうにない平和な国で、発展していて、人は穏やかで…という中立的なイメージがある。もしここが「ポーランドの家」とか「アメリカの家」とかになると全然違うものになるだろうから。逆にドイツ在住の日本人からすると日本語がしゃべれるという安心感もありつつ、いざ行ってみるといろんな国の人が集まっているコミュニティという、どちらにとってもWinWinになっていた」
「とはいえ、ライプツィヒも人口が急増したことでエリア一帯の家賃が高騰しつつあって、ここをいつまで維持できるか…。しかしその一方で、「日本の家にきたい」という日本人からの問い合わせが増えていて、受け入れ体制を整備するため住居を何部屋か借りようと考えている。もちろん、日本の家の移転先も並行して探しています」
■場所(=空間を伴ったコミュニティ)をつくるプログラム~てぶら革命
今後について「けして楽観視はしていない」と言いつつ、次へ向けて耕そうとしている。そのひとつが、ライプツィヒで学んだことの日本での実践だ。
「ライプツィヒで出会って日本の家で一年半ほど一緒に活動した日本人のアーティスト(宮内博史さん)が、鳥取県の鹿野町とつながっていたので、それをつてに鳥取で新たに活動を起こそうとしています。日本での行き辛さがあって海外にきて、こういった活動を知り、関わって…でまた日本に戻って、あの体験をもう一度続けたいという想いがあると思う。でも体験は言葉では伝わらないから、実際に場をつくっていくきっかけとなるワークショップをドイツから自分たちが行ってやろうよと」
この地に外から移り住んできた人の移住をいかにうまくランディングさせるかが今回のテーマだ。彼らが新たな地で生活していくためには、地元の人とのネットワークとそのための場所づくりが必要。移住という意味では国内でも海外でも同じで、まさに大谷さんがライプツィヒで自分の場所をつくったのと同じプロセスを再現すべくサポートしようというものだ。
これが「てぶら革命」という新たなプロジェクトなんですね。
「“てぶら”には、経験はないけど自分の手だけでたどたどしく活動していく、そのプロセスで学んでいくLaernig by doing、手が空いているから繋がれる、そんなイメージを。“革命”には、なにか物事を始めるときに(まず予算とか、まずどこかに所属するとかでもなく)てぶらから始めること自体が革命的なのではないかという意味を込めています」
さらに今年は、ライプツィヒの日本の家の事例と、鳥取での3週間のワークショップの実践、その他の都市における場所づくりの事例を一冊にまとめてクラウドファンディングで出資をつのり、出版する予定だ。
「革命は常に辺境からはじまる」という言葉がある。すごくいい言葉だなと思っていて。現状支配的なシステムから取り残されたところに次の可能性が眠っていると思うので、鳥取を皮切りに、そういう地を行脚して革命を起こしていきたいなと思っている」
■人々の「生活」を取り戻す実践
2012年にまとめた日本の家の活動報告冊子のあとがきの大谷さん自身の文章を引用しよう。
─ライプツィヒの空き家に暮らし仲間と共にプロジェクトを進めていく上で、「場所をつくる実践」は、人間の「生活力」と深く結びついていると実感しました。これは自分たちの生活に必要な物と場所を自分たちで作るという力、またネットワークを広げコミュニティをつくる力であって、我々が本来もつ基本的な能力といえると思います。─ 『都市の「間」』あとがきより
そして今、こんな風につなぐ。
「自分の生活半径2~3mのところからはじめる。実感を伴った場所をいかに自分がつくれるか/参加できるか、からはじめるしかない」
大谷さんのこの確信とも決意ともとれる言葉が、いつまでもわたしの胸に響いている。
【了】
文責:山下ゆかり
※1:2014年、ニューヨークタイムズ誌が「‘New Berlin’or Not, Leipzig Has New Life」という記事で紹介したことがきっかけ
※2:ハウスハルテン(HausHalten e.V.) は、空き家の所有者と使用者の仲介を目的として活動している市民団体。当時、空き家率は50%を超え市全体でも20%弱という状況下で、ライプツィヒ市はハウスハルテンの活動を市内の空き家対策の重要な柱と位置づけた。再生重点地域の空き家に狙いをつけ、所有者にコンタクトをとってハウスハルテンのプロジェクトを紹介し、物件の提供・貸出を促した。ライプツィヒでのハウスハルテンの活動は、空き家再生の先進事例として他都市にスケールアウトしている。(参考:こちら)
【編集後記】
プロジェクト立ち上げ当初からの中心メンバーである大谷さんに、このタイミングでお話しを聞けたのは幸運だった。というのも、これまでの活動を一区切りし次のステージへいくために、大谷さんは我々の渡独と入れ違いで日本に一時帰国されるということだった。インタビューの後その足で発つ予定という慌ただしいなかで、しかし逆にいうと荷造りも済んだ静謐な大谷さんの部屋で(それは日本の家の二階にある)、日本の家を引き継いで任せるスタッフのみなさんと一緒に、この取材は行われた。