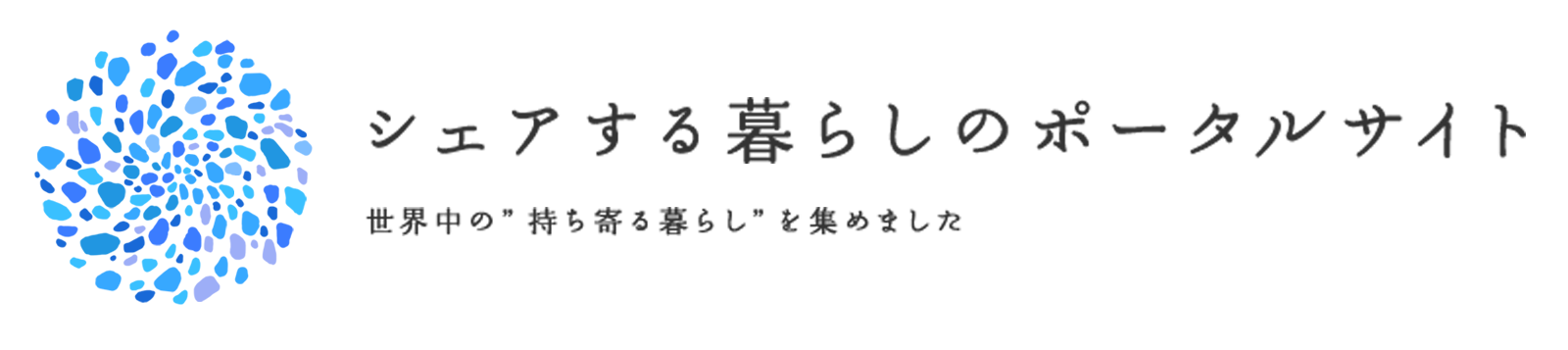飲食店が並ぶ商店街の少し奥にある路地を曲がると、2階建ての木造住宅「三田の家」がある。なんとも「家」といった佇まいである。
三田の家は、築40年になる木造住宅で「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して2006年9月30日から活動をスタートさせている。慶應義塾大学の教員や卒業生を含む学生有志と三田商店街復興組合が共同で運営しているプロジェクトだ。
10人の「マスター」が毎週1日ずつ曜日ごとに場づくりを担当している。留学生との交流、オープンなゼミ、地域イベント、居合わせた人での食事会などを行ったり、時には何もしないで思い思いにくつろいでいることもあり、曜日によって異なるマスターそれぞれの個性が反映された場が作られている。
今回は、慶應義塾大学教員の岡原正幸さんと坂倉杏介さんがマスターをつとめていた2日にわたって三田の家にお伺いした。
味のある木製の格子戸のある建物
緊張しながら三田の家を訪ねると、ドアの開け放たれた玄関には既にたくさんの靴がならんでいた。その日訪れたのは岡原さんのゼミの卒業生が企画した「三田秘宝館」というイベント。年齢も性別も分け隔てないさまざまな参加者が集っていた。イベントでは、セクシャリティをテーマとした赤裸々な意見交換が行われた。
「らしくない」場づくり
岡原先生は学生が周りの仲間を巻き込みながらアイデアを形にしていくプロセスを大切にしており、今回のように学生が自由にイベントの企画を行える機会を与えている。なぜ地域に学びの場を作ろうと思ったのかという問いに対して、「学生たちは大学とは何か、ゼミとは、授業とは何かということを学ぶ前に知ってしまっている。それを超える答えを出してはいけないと学生自身が感じてしまっているからだ」と岡原さんは答えた。
確かにその通りである。私たちは無意識にその場にふさわしい回答や振る舞いをしてしまうものである。その窮屈な枠が取り払われた「大学らしくない」ことの実現を求めて家をつくったのだ。三田の家には、ワインが数本常備されビールサーバーまで置かれている。とても学びの場とは程遠い様子である。

金曜日のマスターを担当している岡原さん
インタビューの合間にもあちらこちらからマスターである岡原さんへ声がかかり、話が中断される。
「三田の家とはこういうもの」と岡原さんは笑いながら言う。授業をしていても、何をしていても、こういうことが起こるそうだ。しかし、岡原さんは積極的に邪魔をして欲しいという。
大学という学びの場では一貫したものが体系的に語られるが、実社会ではそもそもそれが形として成立することは難しい。三田の家に集まる様々な人がもたらす「ノイズ」が、この場のおもしろさのように感じた。ゼミ生のYさん(20代女性)に三田の家の印象を聞くと「ここは不思議な人の集まり。勉強している感じはまったくない」という答えが返ってきた。学生たちはそのノイズを自然と受け入れ楽しんでいるようだ。「学校と家の中間の場所」―。まさに、岡原さんの狙い通りである。
枠をとりはらうことから生まれるつながり

キッチンのテーブルには料理とお酒が並ぶ
これだけたくさんの人が集まる場のマスターとして大変な気遣いがあるはずだ。そう思い、マスターをしている時に気をつけていることは何かと聞くと、なんとも驚きの答えが返ってきた。
「何もしないこと」だと岡原さんは語った。
「放っておいても人と人は繋がっていくと思う。なんか繋がりにくいと感じるならば、お互いにこうあるべきだという枠を作ってしまっているから。それが崩れれば、つながりを作るまでもなく自然と人はつながる」
つまり互いにありのままを認め合うことから相手を自然に受け入れることができるというのだ。周りを見渡すと、どんな人も分け隔てなくお酒を飲み、会話を楽しんでいる様子が見受けられる。
三田の家では社会にある常識や枠組みは当てはまらない。先生も学生も近所の人も、対等な立場でそこにいて、互いに学び議論し合っていることが感じられる。誰もその立場や振る舞いを意識していない、自然体の関係性が生まれていると言えるだろう。誰しもが持つ社会の常識や枠組みを自然に脱ぎ捨てられる場が「三田の家」なのではないだろうか。
受け入れてくれる場所
後日坂倉さんがマスターをしている三田の家を訪れた。ドアを開けるとさっそくキッチンでは食事の準備が進められていた。
この日は近所に住む高校生の家庭教師をしていた学生の卒業にあたって、高校生のお母さんがお祝いの食事を用意してくれるようになった。それをきっかけに「何かから卒業したい人の会」というテーマのイベントになった。

キッチンでは大量の食事の準備がされている。この日のメニューはタイカレー
三田の家に訪れている人たちにインタビューをしているとみんなが口を揃えていう言葉がある。
近所に住むGさん(40代女性)は三田の家を「誰でも受け入れてくれる場所よ。ここに来れば会話と仲間がいるの」と言う。Gさんは毎日のように三田の家にきては、たくさんの人との会話やその場を楽しんでいるそうだ。
留学生(20代男性)は、毎週月曜日に行われるゼミに参加しているそう。「留学したての頃、寂しさを埋めてくれる仲間と深く語り合う場がほしかった。三田の家にくれば、誰かが話を聞いてくれる」と言う。
卒業生のHさん(20代女性)は、卒業した後もふらっと戻ってこれる場所だと言う。学校には顔を出しづらいが、三田の家には戻ってくることができる気軽さがあるらしい。
三田の家では、最初のうちはかしこまっていても、靴を脱ぎ床に座ると不思議なことに初対面の人同士でも気軽に話すことができるようになっている。気づくと社会のことや暮らしのことなど様々な年代、志向の人と意見し合っていたりする。参加者がそれぞれ自然と相手を受け入れ、共に学び合う姿勢がそこにはあるようだ。
それぞれの自主性を認める場

テーブルを囲みさまざまな会話が繰り広げられる
三田の家には明確な目的はない。
まちづくりの場であると定義すると、訪問者のふるまいを制限することになってしまうからだそうだ。坂倉さんは何もしないということを「それも立派な自主性だ」と言う。普通、場が与えられると何かしなくては、さて何をしよう、と考えてしまうものである。しかし、三田の家では「何もしないこと」までもが認められているのだ。
大学という学びの場では学生は受け身になりがちである。
しかし三田の家を訪れる人々は「なにかしらの意味」を各々が持ち、自主的に学びを展開させている。自らの考えを他人に伝え議論する、これが社会とつながった学びであると言える。三田の家に明確な目的がないからこそ、この場が自由な学びの場になっていると言えるだろう。
三田の家の成り立ちがそうであるように、そこに訪れる人々は着飾ることなく自然体でいることができる場なのだろう。だからこそ、ここには不思議な繋がりの連鎖が生まれているのではないか。誰かの為でもなく、自分の為だけでもない、自然な人と人との関係性が保たれた場のように感じた。
ゆるやかな「学び」を通じて、よりよいコミュニティを育む秘密が、ここ三田の家には詰め込まれているように思う。【了】
文責:馬渕かなみ