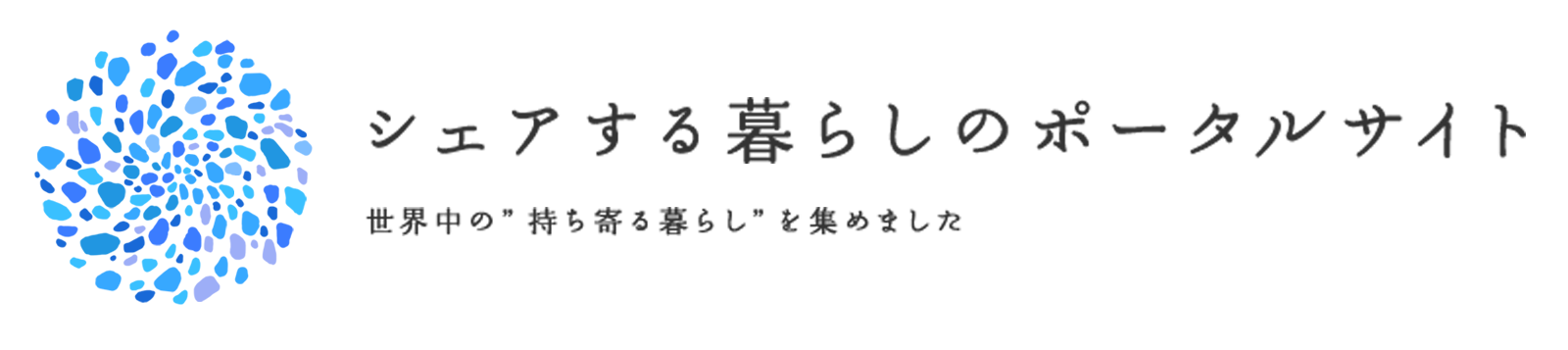横浜の丘の上で住宅街の中に佇むシェアハウス、ウェル洋光台(以下、ウェル)。コミュニティ崩壊の危機に瀕しながらも、現在では入居待ちが出るほどの人気ハウスとして蘇ったことについては前回の記事(リンク)で簡単に触れた。ウェル洋光台を「善意と好意で成り立つ」現在の姿にまで押し上げたエネルギーについて、今回は三恵子さんという暮らし手にお話を伺った。
(前回の記事はこちらから)
GiverとTaker
三恵子さんは、前回の話題にも出ていたウェルの改装工事の時期に重なるように滞在した、約4ヶ月という短期の暮らし手だ。職業は学校の先生で、個人的に氣学を学んでおり、自らの行動規範ももっぱらそれに基づいているという。でも普段はその立場や知識をひけらかすこともなく、丁寧な物腰で人と接する。
訳あって、現在の住まいである大阪から「東」を目指してやってきたところ、短期の住まいとして突如「シェアハウス」が閃いたのだそうだ。エリアを横浜に定め、いくつかのハウスとコンタクトを取ったところ、ウェルのコンセプトや考え方が自身の意識とシンクロした。満室だと言われたものの、「机の下でもいいから」と頼み込んで住まわせてもらったという経緯がある。
そんな三恵子さんが、ウェルでの暮らしの秘訣を、「Giver」という概念で解説してくれた。
「与えるものが与えられる、という言葉があるのですが、ウェルはこの言葉を自然な形で実践している場所ではないかと直観しました。私がこの言葉を知るきっかけとなった「Give&Take」という本の中で、Giver(ギバー)とTaker(テイカー)という概念についての描写があります。簡単に言うと、Giverは相手(他人)を優先する人、Takerは自分中心な人です」
「ウェルには、みんなが持ちよって使っている共用物がたくさんありますが、それが無くなるということがない。つまり住人にTakerがいないし、来ないんですね。たとえいたとしても、ウェルで生活しているうちに変わっていく、そんな風に感じています」
「実際、ウェルで暮らし始めてから価値観が変わったという人は少なからず居るんです。生活の場でも仕事の中でも、人に喜んでもらいたい、人との関わりを考えたい、という風に生きるようになった。それはつまり他者へ対する意識が高まったということで、全体のことを考えて動いているということです。これは、「Giver化している」と言うこともできます」
「Giverが集まるウェルを実証するものとして、例えば「何かをやり始めたら早い」というウェルの特徴があります。庭に菜園を作るのも、改装工事で壁にペンキを塗るのもそう。自分のことだけ考えていたのでは、なかなかこうはいきません。自分が住まない部屋のペンキなんて、普通は塗りませんよね。バイト代も出ないのに(笑)」
“善意を信じる態度の強さ”
三恵子さんは、ウェルを見学に来た時、その雰囲気がすぐに気に入ったという。特にキッチンでの料理の持ちよりの様子を見て「シェアする」という意識が自然な形で場と人に馴染んでいると感じたのだそうだ。
「ウェルでの核となっている、「シェア」という意識がどこから来るのかな?という問いは私の中にもあります。とにかく、ウェルというコミュニティの中でその意識がとても自然な形で存在しているんですね。私が無理に頼み込んでここに住まわせて欲しいと言った時、誰からもどこからも深い追求はありませんでした。共用の部屋に住んだり納戸で寝泊まりしたり、新しく増設したばかりの部屋に住まわせてもらったりしたのも、ウェルが全体として受け容れてくれたからこそ可能になったこと。それはウェルに、Giveとシェアというコミュニティの芯があったからだと思っています」
「ひとつには、ボランティアで管理人をやっている戸谷さんのコンセプトが強力だから、というのはあるでしょうね。ルールがないことがルール、というのもそうで、戸谷さんが管理人になったとき、ハウスの中の張り紙(注意書き)の類を全部撤去したそうなんです。「トイレは綺麗に使いましょう」とか、「洗い物はちゃんと棚に戻しましょう」とか。そういうのは全部、各自が自発的にやることだから張り紙したくないし必要ない、というのが理由だと聞いて、私は正直、「それはわかるけど理想だよね」と思ってました(笑)。でも実際には、張り紙がなくても生活はうまく回っている。人の善意を信じる、という簡単ではないところに踏み込んでいるなということを感じます。その態度の強度に、私は感銘を受けたんですね。そういう戸谷さんの考え方というかアイデンティティーが、周りの住人にも影響を及ぼしているのかもしれません」
ぶつかり合うことで、自分のいびつさが研磨されていく
前回お聞きしたお話の中でもキーマンとして登場した、ボランティア管理人の戸谷さん。やっぱり、今のウェルができたのは戸谷さんの力によるところが大きい? と素朴な疑問をぶつけてみたところ、三恵子さんは少し考えて「答えになっているかどうかわかりませんが」と前置きした上で話し始めた。
「他人に喜んでもらいたいし、人が喜んでくれると自分も嬉しい、というのは誰もが持っている性質だと思うんですよね。違いは、それを意識しているか否かということだけで。あとは、そういう性質に共鳴するか、できるかということも大きい。共感じゃなく、共鳴。人を音叉(注)に例えたとき、共鳴でなく打ち消してしまう人は難しい。ただ、それが意図的ではなく、音叉自体に偏りがあったりいびつな形になっていることは当然あるし、それは自分自身では自覚できないものなんですよね。そこに他人がいると、そのことを認識できやすい。自分自身のいびつさが、他人とぶつかって初めて分かる、ということです」
「ウェルっていうのは、そうやってぶつかり合うことが当然、という共通認識が持てている場なんですよね。ぶつかり合うことで研磨されていくものだよね、という前提がある。これが、外の世界だと難しい。なぜなら競争社会だから。競争社会は、ぶつかり合ったら蹴落としていくという文化ですから」
注:音叉(おんさ)…特定の周波数を発生させる器具。楽器の調律などに利用される。
音叉同士を近づけたとき、同じ周波数なら共鳴するが、周波数が違えば
打ち消し合うこともあるという性質を持つ。
個性を持ちより、補い合うという文化
すぐ分かったつもりになるし、思い込みが激しいと自分を評する三恵子さんは、だからこそ実践ということを起こしにくい性質なのだと自己分析しながらも、話を続ける。
「自分はできていないと思っていたことが、実はできていたという発見がありました、私は。それもウェルの特徴だと思います。住人が、それぞれ持っている個性を持ちより、交換し、補い合うということが自然とできている。多様性を尊重し、批判をしないという戸谷さんのテーマが生きていると、ここでも感じます。結果として、なんの役にも立たない、あるいはマイナスだと思っていた自分の或る部分が、誰かを補うことができるという発見も起きる。そうやって、自分自身の再発見だったり、再生ということが起きるんです」
「そもそも、ウェルでは、人生や人間の変わり目にある人が住人になっているように思えます。そういう人にとって、再発見とか再生ということは、背中を押してくれるものになるんです。
例えばハウス内で使う建具や調度品なんかにしても、戸谷さんがどこからか持ってくるんですよね。古材とか、こわれかけのアンティーク調なものを。昨日は棚にオイルをかけてましたけど、多くの場合、そんな風にしてひと手間かける。古材の棚は、「味のある」棚に甦らせる。古いものを取り出してきて修繕し、それに新しい役割を与えていくというサイクルが出来上がっている。そして、それは人に関しても同じことが起きているんじゃないかと思います。ほんのひと手間をかけるように、変わり目にある人の背中をそっと押してあげるような」
生活の場を共にしているからこそ起きること
短期の住人でありながらも、戸谷さんが不在時の管理人代行や、作業工程がもつれていた改装工事の進行管理を買って出たりしていたという三恵子さん。そんな、全体を俯瞰できる位置から観たウェルはどんな場所だったのだろうか。
「人は誰でも、何かしらの問題を個々に抱えていると思うんです。そして、それをそれぞれに乗り越えようとしている。ウェルという場は、そんな人たちの下支えとなっているように感じます。例えば問題を乗り越えようとしたとき、壁にぶつかることがある。でも、ここではウェルという場があるおかげで行き詰まらずに、別の見方や道を発見できたりする」
「ウェルの住人たちと、サークル等の集まりとの違いを考えてみると、少し分かりやすくなるかもしれません。サークルというのは、共通の目的や趣味嗜好を持った人が集まりますが、ウェルの場合は一定の傾向はあるにせよ、基本的にはバラバラです。でもそのバラバラなままで、パズルのようにぴたっと組み合わさることがある、あるいは、住人の特性が掛け合わさって化学反応を起こしたりする。生活の場という舞台を通して、それぞれの仕事やこれまでの背景も絡み合い、人生が、人間が丸ごと見えてぶつかり合って、それが影響を及ぼし合う。それは、サークルの集まりとは違って、生活の場を共にしているからこそ起きやすくなることなんだと思います」
「与えること」がもたらすエネルギー
人と人とが掛け合わさる。そこから何かが生まれる。
それが、前回の取材と共通して抱いた感想だった。情報化された人間ではなく、丸ごとの存在としての「人」。ウェルは生活の場だからこそ、必然的に丸ごとの自分が剥き出しになる。背景も考え方も違う赤の他人同士が剥き出しで集まれば、当然ぶつかり合いが起きる。そして、そのおかげで生まれるものがある。
悠作さんはそれを「きっかけ」と呼び、三恵子さんは「再生」と名付けた。
何の役にも立たない、むしろマイナスだと思っていたことでさえも、自分の持つリソースになる。それが他人と掛け合わさることで、自分のマイナスが誰かのプラスになり得る。その事実が、バラバラになりかけていた自分自身を繋ぎ止め、新しい形に進化させていく。三恵子さんは、ウェルでの短い暮らしの間に、そういう実例をいくつも見て来たのだという。
信じていたものが崩れ、自信をなくしたときだって、それを受け容れてくれる。誰もが、どんなときでも、「与えるもの」を持っている。生活の場を舞台に、人と人とが丸ごと交わることで、自分が持つ「与えるもの」を発見できる。だから、誰もが、Giverになれる。与えることで自信を与えられて、そうやって人は再生していける。ウェルという場には、そんな循環がある。Giverを育む土壌になっている。それはもはや、ひとつの生態系だとさえも言える。
次回は、現在のウェル洋光台のキーマンである、自称「ボランティア管理人」の戸谷さんにインタビューを行うことで、この連載の区切りとしたい。【了】
(村上 健太)